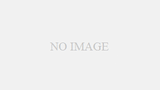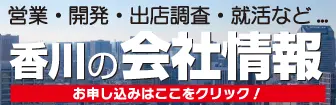大阪城 秋祭り2024(大阪城パークマネジメント(株)主催)に、日本遺産「知ってる!?悠久の時が流れる石の島〜海を越え、日本の礎を築いたせとうち備讃諸島〜」の岡山県笠岡市(栗尾典子市長)、丸亀市(松永恭二市長)、土庄町(岡野能之町長)、小豆島町(大江正彦町長)の2市2町が参加した。
現在の大阪城の石垣は、六甲山、生駒山、北九州に瀬戸内の島々から切り出された花崗岩で、徳川秀忠、家光時代に築かれた。豊臣秀吉時代の石垣は、地下に覆い隠されており、2025年には、豊臣大坂城の石垣公開施設のオープンが予定されている。
天守閣前イベントとして、石工らが唄ったという北木島の石切唄の披露や石材を使ったワークショップをおこなったほか、土庄町では、巨石を運んだ木製のソリ、修羅(しゅら)と石材3・8tで築城の様子を再現した。修羅(600㎏)は、仏典から帝釈(大石)を動かせるのは阿修羅(修羅)だけという伝承から名付けられている。

土庄町商工観光課では、修羅引の実演をおこなった際、最初は子ども達が数人、徐々に大人、またインバウンドらが増え、20名程でようやく動き始めたと話す。 その昔、小豆島など瀬戸の島々から、どのように巨大な石が大阪まで運ばれたかは、今現在も調査中。400年の時を超え、大阪城で、瀬戸内海を渡った石を運ぶ風景が見られた。